 機関紙
機関紙 2010・9月・NO.332
2010・9月・NO.332| INDEX | |
| ●2010ヒロシマ平和行動に参加して |
|
| ●生活クラブ福祉基金賛同者集会 |
|
| ●福祉基金助成先紹介 |
|
| ●2010年度消費委員長研修 |
|
| ●情報BOX |

忘れない あの夏の日を
 原爆投下直後のヒロシマ(平和記念資料館に展示されている写真) |
| 真っ青な空。セミしぐれがあたリー面に響き渡る。肌を突き刺すような暑さ… 音もなく一瞬の閃光。もくもくと巨大に立ち上る黒いきのこ雲。地上の全てを吸いこんだ炎の柱。奪われた数十万の命。あの原爆投下から65年。今年は中高生
3人を含む総勢10名が8月5日から7日までヒロシマ平和行動に参加しました。 ※下に報告文掲載 〈本部文化委員会〉 |
組合員から託された折鶴を手にする参加者 |
8月6日午前8時15分、 原爆投下時刻にダイ・イン |
死者を悼む灯篭流し。犠牲者の中には強制 連行された朝鮮人や米兵捕虜も含まれている |
海上自衛隊呉基地。現在は米国の核搭載可能な艦船が寄港する |
2010 ヒロシマ平和行動に参加して |
忘れてはならない真実
海軍地下工場跡。暗く狭いトンネルのよ うな場所で女性たちが働いていた |
原爆ドームを初めて見たのは 小学校6年生の時、担任の先生 が撮った写真でした。当時は漠 然と感じられたその建物も、8 月5日に実際に目にすると鳥肌 が立つほど存在感がありまし た。存廃を巡って様々な議論を 呼んだ場所ですが、被爆当時の 面影を残したまま保存されてい ます。 8月6日は「ダイ・イン」。朝 から暑い日で、蝉の声を聞きな がら目を閉じ、当時の風に耳を 傾けながら平和を祈りました。 そして今年は「被爆式典」 に、 国連総長・アメリカ・イギリス・ フランスの大使が、初出席しま した。
「ヒロシマスタディ ツアー 2010」では、
8月7日、
この旅で初めて耳にした、旧海軍の特攻として志願した14、 15歳の少年兵の「回天」(人間魚雷)や、母親が妊娠初期で被爆し誕生した「水頭症」の子ど もたちのことを知り、涙が出そ うになりました。
戦争が何故いけないことなの かを、戦争を知らない世代に正 しく伝え続けることが大切だと 強く感じる旅でした。真実は、 決して忘れ去られてはならない ものなのです。
僕にできることは 語り継ぐこと
| 被爆者証言のつどい。証言者の木村さん(前列中央)と斉藤君(前列右) |
白石支部 齊藤 元気(中3)
ヒロシマ平和行動に参加し、 学校では学べない大事なものを 得ることができました。 今回、一番印象に残っている のは平和記念資料館です。そこ で原爆投下までの戦争の歴史と 原爆の恐ろしさを学びました。 展示されている被爆した人た ちの遺品は見ているだけで胸が 痛くなり、色々なことを考えさ せられました。普通では考えら れないくらいのやけどをした人 が、どれほど痛く苦しい思いを して生きていたかと想像すると 涙が出そうでした。
そして、今回被爆者の木村ひ ろみさんの証言を聞き、より恐 ろしさを感じました。当時まだ 小学生だった木村さんは、家族 を亡くし、孤児になりました。 目の前でお父さんと妹が死んで いったそうです。その後、キリ スト教に出会い、心のケアを受 け、これから生きていく人にこ の体験を伝えていきたいと思っ たそうです。
いまだに心のケアがされず、 このことを誰にも話せない人が 数多くいるそうです。木村さん 自身も60年間、語ることができ ませんでした。そんな中、僕は実際に被爆者である方の話が聞 けて良かったと思いました。
僕は学校の社会科の授業で、 少しだけ広島の原爆のことを学びました。教科書を読んでも、 どれくらい恐ろしいものなの か、どんなに苦しく辛い思いを している人がいるのか知ること はできません。でも、実際に原爆を落とされた広島に行き、戦 争の恐ろしさを知って、二度と このようなことを繰り返しては いけないと強く思います。
僕は今まで平和について深く考えたことはありませんでした。もしかしたら戦争が起きる なんてありえない、関係ないと 正直思っていたのかもしれませ ん。でも戦争をして良くなるこ とは一つもありません。人の体を、そして心を傷つけ、国もポロポロになるだけです。戦争は、 何の罪もない人たちを傷つけ、 人の命を奪います。僕にできることは、将来大人になった時に、 若い世代に伝えていくことだと 思っています。
政治家になり国を支え、変 えていくことはできないかもし れないけど、僕は原爆が落とさ れた国である日本に生まれ、生きているので、これからも、どの国の人たちよりも平和について深く考え、学んでいきたいと思っています。
| 生活クラブ福祉基金賛同者集会 |
| 7/28 札幌教育文化会館 |
2010年度の総代会で、「福祉基金の賛同金を1人70円から100円にしたい」という提案が行われました。しかし、話し合いが足りないのではないか、提案が浸透していないのではないかという意見があり、採決の結果保留が多く、可決にはいたりませんでした。福祉基金賛同者集会の第1回目はこうした結果を踏まえ、いろんな思いを語り合う場、改めて福祉基金を学び合う場として開催され、専務理事 池内信さんの講演「生活クラブの福祉について」に続いて、参加者による活発な意見交換が行われました。
| 生活クラブの福祉について |
●協同組合と福祉
生活クラブの福祉基金を始めるにあたっては、2年間、 組合員の中で話し合ってきました。その中で繰り返し出てきたのは、「なぜ生活クラブが福祉に取り組むのですか」という意見でした。
我々のような消費協同組合は、消費者が望む食品を中 心とした良い物を共同購入する、もしくは売っているとこ ろというイメージがあります。 しかしそれは手段であって、 協同組合の根本の目的は、みんなで力を合わせ、地域社会 を良くしていこうというとこ ろにあるのです。
では、世の中を良くしていこうと考えた時に、これからの日本社会の最大の課題はなにか。それは少子高齢化です。 2050年には、現役世代の 1人が高齢者1・5人を賄っていかなければなりません。働く人がいなくなる、納税者が 減少し、税金を使う高齢者が 多くなるという構造になり、 当然、福祉についてもお金も 無ければ担う人もいないという状況に陥ります。
生活クラブが提案しているのは、こうした社会に対して、 市民自らの力で地域福祉をつくって行けないかということです。市民側の領域を広げていくことが、儲け主義に走る企業の福祉や、画一的にならざるを得ない公的福祉に対しての牽制作用となる、というのが福祉に取り組む理由なのです。
●生活クラブの福祉事業・活動
2000年に、初めて生活 クラブが本格的に福祉に取り 組んでいくという宣言をしました。第7次中期計画では、 たすけあい共済・デイセンター・福祉基金の取り組みを、 3つの柱としました。
01年に、デイサービスセンター「デイこたけ」の開設と、 たすけあい共済の導入。03年 から福祉基金の取り組みが始まり、04年には、居宅介護支 援センターを「デイこたけ」 に併設しました。地域には、 たすけあいワーカーズもあり、 市民による福祉の道具を幾つもつくり、見えるようにしてい こうという構想の下で始めています。
05年には、親子ひろば「ほっとたいむ」を開設。孤立している母親たちが顔を合わせる場をつくりたいという趣旨で始めたひろば、これも福祉基 金が支えています。
●福祉基金についての新たな提案
福祉基金を始める時に、大きな議論があったという話はご存知だと思います。最初、 理事会提案は全員参加で100円 でしたが、議論の末、最終的 には現在の任意参加で1人毎 月70円の拠出金となりました。
今年、福祉の本格的取り組 みから10年を迎えます。賛同 者の伸び悩みもあり、ここで もう一度仕切り直し、拠出金 を当初考えた100円とする。そ して、この提案を契機に、改め て賛同者の拡大を目指したいと 考えます。
賛同者がもし3千人になっ た場合、年間の福祉基金の総 額は最大720万円(CO・ OP共済事務手数料含む)。そのうち、地域で活動している 団体への助成分(3割) が 220万円、生活クラブ福祉 事業・活動分は500万円の 使用が可能になります。
例えば、それを基に新しく 次のような福祉事業も考えら れます。
・ほっとたいむ3ヵ所目の開設
・福祉電話
・コミュニティサロン
・地域食堂
もう一つ、付け加えておきます。助成金には、いろいろな活動をしているボランティア団体からの応募があり、裾野を広げる意味では意義があ りますが、市民事業として始 めようとする人たちにとって 5万、10万というのは残念ながら大きな力にはならない金額です。
場合によっては50万円という規模にする。また、単年度ではなく、2年間という助成もできれば良いと思います。 市民事業として、本格的に福祉を始めたいという人たちに とっては、かなり有効な力になるだろうと考えています。
| 福祉基金賛同者の声 | ||
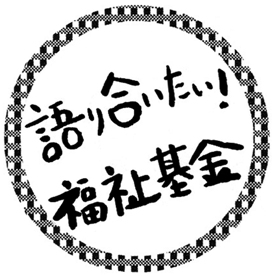 |
福祉基金は、市民が主体となってつくる福祉事業に、生活クラブが カを貸していくという取り組 み。それを広げていくのか、現状維 持なのか、縮小するのか、総代会の 中では皆さんの考えがなかなか聞 けなかった。いずれ私たちも高齢者となり、社会的サービスが必要となってくるが、行政が行なっている福祉は、私たちが望むものと食い 違っていることもあると思う。市民が本当に必要としているサービスをつくり出し、地域に提案していくことは、未来への希望につながる。 | 値上げの提案が否決されたのはすごく残念。福祉基金に賛同している人は、この取り組みに共感しているから賛同しているのだと思う。よりよい暮らしを求め、もっと福祉基金 を大きくする活動を進めていき たいと思った。ただ、否決され たことで話題にすることが多く なり、支部で福祉基金の目的に ついて改めて考えるきっかけになった。今後も継続して話題にしていきたい。 |
| 親子ひろば「ほっとたいむ」 輪厚会場  |
福祉基金に加入していたつもりが、未加入だったことに気が付き昨年入った。 今回、支部の賛同者にドキドキしながらこの集会への参加呼びかけと、意見聞き取りの 電話がけを行なったところ、 10人中10人が賛成という意見 だった。むしろ自分たちのやっ ていることは良いことなんだ、という自信につながった。 | 総代会では、70円から100円 に値上げしたいという文言にしか受け取れなかった。しかし、福祉基金を広げていくことが大事なことは十分認識している。支部では、1%ずつ しが伸びない基金でいいのか、 もっと発展させるためには1人 がたくさん拠出するのではな く、たとえ10円でも1万3千人の力を結集する方が良いので はないかということを話して きた。多くの人の賛同を得る ことが大事であるならば、もっ と方法があるのではないか、みんなで話し合うことが必要で はないかと提案に反対した。 |
| 生活クラブは食の生協といっているが、食を守る ためには、それをつくりだす 環境も守らなければならな い。また、環境を守るために は、安心して暮らせる社会 がなければならず、福祉は そのための取り組みなんだ と思う。総代会で反対意見 が出たことにより、もっと伝 えていかなければということが分かり、良かったと思う。 | いきいきライフ講座 |
私が総代会で反対したのは、もっといろいろな人に伝えていけば、賛同してもらえると思ったから。現在育児休暇中で、委員になって福祉基金のことも知ることができた。自分のような人がたくさんいると思う。戸配の人や仕事を持っている人にも伝わるような何かが、もっと必要ではないか。 |
| 班会で値上げの提案について話し合った。まず、賛同者を増やすことを考え、それでうまくいかない場合、値上げを考えてはどうかというのがみんなの意見だった。でもこの集会に 参加して、班の意見は違う なと思った。もっと大きな 何かが出来るのであれば、 100円で良いと思う。福祉基金を広めていこうという建 設的な声が圧倒的に多いの で、意見を出し合い、それ から出発するということで は良かった。 | 介護教室 |
| 福祉基金 助成先紹介 |
一人ひとりの自立をめざして
NPO法人 共生の森(札幌市)
| 助成金で購入したハウスで野菜を収穫 する斉藤さん。ゴーヤやトマトが緑の 香りを放っていました |
精神・知的障がい者のほとんどは、大人になるまで施設や病院で過 ごしています。当事者や保護者は、 自立して地域の中で生活すること を望んでいますが、大きな病院や 施設に併設している大規模な事業所では、一律に活動するため一人 ひとりに合った訓練が十分にでき ません。自立に向けた細やかな対 応ができる小規模な事業所は、市 内では石山もしるだけだそうです。
現在の利用者は30代の男性2名 で、通所をきっかけに今年の春か ら一人暮らしを始めました。月曜 から土曜まで、南区内からバスに 乗って通ってきます。そうやって 生活のリズムをつけ、家事などの 機能向上を目指し、自立できるよ うに訓練します。また、庭や畑を 利用して、花や野菜の栽培をして います。収穫し調理することで家 事を身に付けることができます。
利用者はその日の体調に合わせ、 活動します。取材した日は、8月 の真夏日、「今日はやる気が出な いようですね」と斉藤さん。でも、 訓練を強要することはありません。 二人は思い思いの場所で、静かに 過ごしていました。
自立支援法では、生活訓練は2 年しか利用できませんが、二人は いつまでも居たいと言ってくれま す。「今後は、就労支援も提供し、 長く利用できるようにしたい」と、 成田さんは始まったばかりの活動 に夢を膨らませています。 (岩野)
多くの親子に絵本の楽しさを伝えたい
NPO法人 北海道子育て支援ワーカーズ (札幌市)
| 夏休みに多数の親子が来場した厚別区 大谷地の親子ひろば「ほっとたいむ」。 みんなで読み語りを楽しみます |
主な活動は、保育事業、厚生労働省から委託されている病児・ 緊急預り対応基盤整備事業、親子が集う広場や「とんとん図書室」 の運営など。市内3カ所の常設図書室では貸し出しを行い、遊びの広場でも絵本コーナーを設けてい ます。そのため多くの本が必要で、 今回の助成金は約70冊の絵本の購入に充てられました。
「ひろばに遊びに来て、たまた ま絵本を眺め、それがきっかけで 親子で本好きになることも多いん ですよ」と、図書担当の小林玲子 さんは話します。スタッフが楽し そうに本を読んでいると、それに ひかれて子どもも読み、その姿を 親がうれしそうに眺めます。そんな風に、本が親子のコミュニケー ションツールになっています。
お母さんたちからは「絵本を かじったり破ったりすることがあ るので、管理の厳しい公立図書館 からは借りにくいけれど、ここな ら安心して利用できる」という声 をよく聞くそうです。「私たちは、 そのまま返却して大丈夫ですよと 話しているんです」と小林さん。 「年齢に合う本の選び方を教えて ほしい」「こんなに小さい時から 本に興味があるとは思わなかっ た」など、スタッフといろいろな 話をしながら本を借りられるのも 特長です。
小川さんは、「これからもお母 さんと子どもたちに寄り添ってい きたい。多くの親子に楽しんでも らえるよう本を増やし、活動を継 続させていきます」と力強く語っ てくれました。 (谷山)
| 2010年度 消費委員長研修 |
本部消費委員会では、生産現場を知り今後の利用結集活動に生かそうと8月6・7日、十勝の中札内村にある㈱中札内若どり・㈲中札内たまご・JA中札内村を視察し、生産者と交流を深めました。
南支部消費委員長 塩原 めぐみ
鶏肉の加工場 |
鶏肉は傷むのが早いため、何 度も洗浄作業が行われ、保健 所の検査員が全ての鶏の内臓を 見て病気や菌がないか細かく チェックしていました。
精肉にされる前の元気だった 鶏を思うと、かなり複雑な心境 になってしまいました。今まで 何も考えず当たり前のように鶏 肉を食べていましたが、実は作 業員の方々の日々の労働によっ て新鮮な鶏肉が供給されていたことがわかりました。これからは、少しでもありがたく大切に 食べていきたいという気持ちに なりました。
今年6月に行われた国産鶏種 の実験取り組みで、製品化でき た鶏は6割ぐらいだったそうです。その結果をふまえ今後、中札内若どりの担当者が東北の養鶏場に視察に行き、再度実験取り組みをしてから国産鶏種を 供給していくという意気込みを 聞きました。生活クラブの組合員の思いに応えようと努力して くれている生産者の方々に感謝 し、組合員の一人としてこれか らも応援していきたいと思いま した。
北斗支部消費委員長 水野 敏美
| 柳沼さんの白菜畑。雑草が生えても白菜の根を 傷めないよう、無理に草取りはしません |
大きく育った大根を手に、生産者の鎌田さんが説明 |
白菜
雑草に囲まれながらも 力強く育つ白菜は、花を咲か せたように外葉を広げ、蒸散 し熱を放出して暑さから身を 守っていました。作物が呼吸 し、活性していることを実感 しました。
大根
春から秋の間で100万本もの大根を栽培しています。 収穫した大根は予冷も兼ねて 札内川の地下水で3回も洗っ てから出荷しているそうです。
キャベツ
除草剤を使わずに 栽培することは雑草との戦い。 雑草は虫を発生させ、病気を 招いてしまう。それを防ぐた めに手作業で草とりをしてい ました。 私たち組合員に安全でおい しい野菜を供給するための生産者の方々の努力が伝わってきました。
二日目は(有)中札内たまごを 見学しました。
中札内たまごでは鶏を雛か ら育てています。だから飼料 や投薬の履歴が把握でき素性 が明らかです。たまごは鶏の 健康状態や割れ等のチェック をしながら一個一個手で集卵 します。その中でも、汚れや ヒビの無いたまごを選び、生 活クラブのトレーに並べてい きます(写真左)。
この検卵も手作業で行うため生活クラブ担当のスタッフ がいます。こんなに手間をか けてくれていたとは!支部に 帰ってみんなに伝えなくては と思いました。
| 情報BOX |

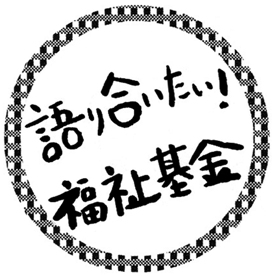 合言葉は 「語り合いたい!福祉基金」
「ふくし」ってみんなのしあわせ・・・ 「誰かに~してもらう」しくみではなく、 「みんなで助けあう」しくみを作りたいなあ・・・
※詳しくは生活クラブニュースをご覧ください。 問合わせ/生活クラブ本部 ☎ 011-665-1717 |
医療保険を選択するポイントを学びます。 日時 10月8日(金)10:00~12:00 場所 かでる2・7 1010会議室 (札幌市中央区北2西7) 講師 生活クラブFPの会 北川陽子さん ●午後1時より個人相談も受け付けます。 主催 たすけあい委員会 石けんで家中ピッカピカに!
台所、リビング、お風呂、トイレをピカピカに! お掃除用の各アイテムの紹介も予定しています。 日時 10月19日(火)10:00~12:00 場所 札幌工ルプラザ調理室(札幌市北区北8西3) ※詳しくは10月1週目発行予定の生活クラブニュースをご覧ください。 主催 石けん運動委員会 |
| 組合員でつなぐリレーエッセイ 「もし、自分に子どもが生まれたら、 色の名前をプレゼントしたい」。ずっと 以前から考えていたという。「誰でもへこむ時はある。僕だってそうだったし…そ んな時、自分の色を観て、元気になって くれたら…」。3日前に父親になったば かりの青年は、私にそう話してくれまし た。モロッコに色探しに行き、見つけ 色の小瓶たちや、イギリスで求めたという美しい石を見せてくれながらのことで した。 小さな生命の愛しさ。小さな生命を胸 の真ん中に包む幸せ。小さな生命を愛し む、親になったばかりの若者たちを見る幸せ。 この7月、3週間ばかり、長女のお産扱いに、東京に行って来ました。武蔵野の面影が残るその街を、住人のように暮 し、娘の未来を想像しました。娘の子ど もが入るであろう、小学校や中学校の 前を通り、そっと覗いてみました。私の 初孫でもあるその子を抱きながら、私が 味わっていたのは、多分、ここ30年に渡る自分の子育ての記憶です。その時間を オーバーラップさせながら、あらためて、 生命の愛しさを再確認したのです。 小さな、でもとても力強い、その子の 名前は、「碧-あおい」です。 豊平支部/花田朋子 |