 |
生活クラブ北海道機関紙 2013 2 NO.361 |
| INDEX | |
| ●2012 国際協同組合年 21世紀 協同組合の未来を学ぶ | |
| ●憲法連続講座(第2・3回)「憲法からフクシマを考える」 | |
| ●組合員グローズアップ 厚別支部 宍戸 隆子さん | |
| ●班っていいね! 白石支部・江別支部 | |
| ●いんふぉめーしょん |
| 森の住人熊の生態を もっと知るために 北大獣医学部の先生を講師にお話しを聞きました。 ヒグマは学習能力が高く一度覚えたエサは忘れ ないので、生ゴミは必ず持ち帰ることや、遭難 した時の対処方法も教えてもらいました。 |
お昼はヤ―コンサラダやニョッキ、イモ餅などたくさんの 畑の収穫物で舌鼓を打ちました。 |
木にクレヨンで絵を描きました。 <主催 森づくりプロジェクト> |
 欧州協同組合の旅 欧州協同組合の旅 21世紀 協同組合の未来を学ぶ 福祉担当理事 小林 恭江 |
2012年は国連が定めた国際協同組合年です。生活クラブ連合会ではこれを機にその価値 を再認識することを目的とした旅を企画しました。12月、私もその一員として、協同組合の起源となったイギリス、協同組合が憲法で保障されているイタリア、スペインの3カ国を訪問しました。
◆3人から協同組合がつくれる社会
ロッチデール博物館 |
このロッチデール先駆者組合から発展した現在のイギリスの協同組合には、金融、保険、生協、学校、農協、自然エネルギーなどがあります。350の小・中学校を行政から委託され運営するコーポラティブ・カレッジなど、その社会的な活動は広がっています。
また、3人の女性が始めた労働者協同組合では、ソマリアの移民女性に向けて、言語や資格の取得のための就労支援を行う社会的企業活動など、3人集まれば様々な協同組合ができる国があることを知りました。
◆社会的に不利な人を支える
かつて解剖室だったバール(立ち飲みカウンター) |
ミラノにあるオリンダ社会協同組合は、レストラン、ホテルなどを、廃止された精神病院の建物を利用して運営しています。お昼時、人々で賑わうレストランは死体安置所を改造したもので、ベンチは障がい者が木工訓練で作ったものです。国の優遇制度やEUからの補助も利用しながら地域の中で障がい者と共に働く場を作りだしていました。
◆協同組合運営の大学も
モンドラゴン・エロスキー生協店舗 |
グループの規模は9万人。120の協同組合が、工業、流通・サービス、金融、教育の4つの分野で運営する巨大な協同組合です。労働を生み出し、保険や共済による生活保障も組み立て、協同組合運営の大学は産業支援の役割を担っています。
協同組合年に、協同労働と地域社会への関わり、そして様々な法制度を学ぶことができました。協同組合の価値が社会的に認められるには、協同組合運営を基本に、福祉・子育てなど地域コミュニティーへの参加を広げることも必要です。ロンドンで聞いた「世界人口の半分の人が参加している協同組合が、力を合わせて何ができるかを模索している」との言葉が心に残りました。
もし、今後日本でも3人集まれば様々な協同組合をつくれるようになったら、どんな仕組みをつくりたいですか。一緒に話してみませんか。私たちの豊かな未来の暮らしのために!
| ■憲法連続講座 「憲法からフクシマを考える」 |
| 3・11の震災による福島第1原発の事故は、いまだ解決の道筋が見えない 状況にあります。大気、大地、海が放射能によって汚染され、「平和に暮らす」 ことを根底から覆したこの事故から、私達は何を学び取り、行動していった らよいのでしょうか。自分と社会との関係を改めてとらえ直し、考えていこ うと開催した憲法連続講座を掲載します。(主催文化委員会) |
 |
札幌市長 上田 文雄さん
上田文雄:市長就任前は弁護士とし て25年間、放射性廃棄物の問題に 取り組んできた。2011年発足の「脱 原発をめざす首長会議」にも参加し、 脱原発の態度を鮮明にしている |
| 誤った情報の刷り込み |
私が最初に原発に関心をもったのは、高レベル放射性廃棄物の問題です。それは、人間がコントロールできないものをつくることへの倫理的懐疑からでした。
1984年、当時の動力炉・核燃料開発事業団が、幌延町に貯蔵工学センターの立地計画を公表しました。原発で燃やした核燃料を再利用するという発想ですが、いくらリサイクルしても最終的に出てくるのは核のゴミ。低レベル放射性廃棄物は無尽蔵に出てきます。高レベル廃棄物は、人間が2、3分そばに いるだけで死ぬような大きな崩壊熱(放射線)を出している物質。それをガラス固化体にして、最終的に幌延の300m地下に埋めるための研究計画です。
寒さが厳しく、雪の多い道北、幌延町の主な産業は酪農です。彼らはここで酪農を営む人たちに、放射線で牛糞を殺菌し、熱を融雪に利用したら良いと言ったんです。誤った情報を提供することをいかに何とも思っていないか。福島原発事故を検証する際、この84年の段階で何が間違っていたのか、とい う本質的な部分がすでに明らかになっていると思うのです。
市民、地域の人に間違っている情報を意図的に繰り返し刷り込む。加えて、地域振興というお金で、人間の弱い部分につけ込むということが国家的に行なわれてきたことは、極めて非人間的ではないかと私は思います。
| 基本的人権の全てを 侵害する原発事故 |
憲法を私たちに引き寄せて考えると、福島原発事故によって何が侵害されたのかを、もっと深く考える必要があります。放射線による人の健康被害・人格権侵害(憲法11条)、放射線源からの退避を余儀なくされたことで発生する財産権の侵害(憲法29条)、避難生活による「十分な生活条件に対する権利侵害」など、憲法10条以降に書かれている基本的人権の全てが侵害されています。
そして一番の問題は、原発政策について「知る自由」が侵害されていたことです。憲法21条には表現の自由、結社の自由ということが書かれてあります。表現をする自由の根源は、知る自由です。さらにもっと大事なことは、情報をもらっても理解する能力がないと何もなりません。ですから、国民が意見を形成するために必要とする力を獲得するための教育を受ける権利、これが保障されなければいけない。憲法26条には、こういったものが規定されています。
1979年にスリーマイル島原発の事故、86年にはチェルノブイリ原発で、原子炉の炉心溶融事故が発生しました。しかし国は、日本では絶対そんなことは起きないと言い続け、私たちは真剣にものが考えられない状況に置かれました。「安全神話の刷り込み」は、思考停止という最大の人権侵害といえます。
また、国は国民の知る自由を充足するために、国民が必要とする情報を分かりやすく提供する義務を負っていますが、しかし、成されてはいません。
原発だけではなく、いろいろな問題が思考停止の危ない状況にあることを反省的にとらえ、札幌市で最初に取り組んだのが「自治基本条例」です。まちづくりに必要な情報を、市民に分かりやすく、積極的に提供していこうという考えからです。
| 私たちがすべきことは |
またこれまで私は、震災の瓦礫受け入れについて「放射性物質が付着していない瓦礫の受け入れには協力するが、汚染され安全性が確認できない瓦礫は受け入れできない」と表明してきました。何度も自問自答しながら、市長として判断する際に最も大事なことは「市民の健康と安全な生活の場を保全すること」との考えに至ったからです。
一方で、市では様々な福島への支援を行っています。現在、福島から1500人の被災者の方を受け入れており、夏休みには子どもたちを招き、放射線から守る活動などにも積極的に取り組んでいます。あるいは、支援活動をする市民ボランティアを市民がサポートするという寄付制度も作りました。また、徹 底した省エネルギーの都市計画を進めるための調査研究も行っています。大きな夢なので何年かかるか分かりませんが、明確な方向性を持って、まちづくりに取り組んでいきます。
さて、泊原発の再稼働問題については、いまだ福島原発事故の原因が明らかにされておらず、また、新しい再稼働基準がないまま認めることにはならないでしょう。原発は将来に対して責任の持てないエネルギーの使い方です。その利便性を享受し、後始末を後世の子どもたちに押し付けざるをえないこと自体、悪しき科学技術の存在ではないかと考えます。
福島原発事故の問題を、同じ人間、仲間として真正面から受け止め、市民の皆さんと様々な活動を通して連帯していきたいと思います。 (取材/笹山)
◆第3回講座 2012・12・1 毎日札幌会館
 脱原発デモってどんな意味があるの? |
今日は憲法講座として話をしますが、実は私は憲法が好きではありません。大学生時代、法律を学び判例を読むうちに、「結局、国を相手に訴訟を起こしても原告側が勝つことは、まずあり得ない」と気付いたからです。
そこで法律ではなく政治学の研究を進めてみると、国によって原発反対運動は強かったり弱かったりと違いがあることがわかりました。日本では、これまでデモ参加者は「変わった人」として見られていたと思います。つまリデモに参加しにくい国です。これは明治憲法でデモが抑制されていたことがそもそもの原因なのですが、戦後、現在の憲法になり合法化されたものの、なお人々の意識が以前と変わらなかったためです。
しかし福島第1原発事故後は人々が立ち上がり、官邸前デモの参加者は12年6月頃から爆発的に増加。大飯原発再稼動後はさらに拡大しました。このデモにより、当時の野田首相は同年8月、歴史上初めてデモ参加者と面会しました。また、9月には新エネルギー政策の原案として、2030年代に「原発ゼロ」を目指すと明言。これは民主党政権に於いて、デモの力で成し遂げた大きな成果です。
この10年私自身、デモにはどういう意味があるのかと、反戦平和運動に関わる中で考えてきました。また、今回の脱原発デモでは、「デモをやって何になるの」と周囲に言われ続けてきましたが、私 はデモや社会運動は、政策をそのままにせず、政治が取り組むべき課題は何かを市民が示す方法だと思います。
例えば現代は、グローバル化により遺伝子組み換え食物など多国籍企業の商業主義が無制限に入り込んだり、企業が原発の立地場所を決めてしまうといった、リスク社会に私たちは置かれています。また、政府が示す政策は、政治家の都合で決められている場合もあります。このような状況の中、全てを上に任せるのはまずい。デモは社会運動には欠かせない、下から提案していく手段なのです。 デモは友人、知人のネットワーク、職場単位、あるいは組合を通すと参加しやすい。最近ではソーシャルメディアの影響で、個人参加も増えています。身近に原発問題を共有できる人がいなくても、デモで同じ考えの仲間を見つけることができます。デモは、いろいろな市民団体が集まって、混ざり合い、多様性があると良いと思います。参加者が多ければ効果が高まるからです。 (取材/谷山)
| 組合員クローズアップ |
厚別支部 宍戸隆子さん | 「恐いのは、事故さえも 忘れられてしまうこと」 |
| 社会的な活動をしている生活クラブ組合員を紹介する「組合員クローズアップ」。その第1回目は、2年前の福島第一原発事故により、福島県伊達市から北海道に自主避難した宍戸隆子さん。避難者同士をつなぎ、支える活動を続けている宍戸さんに、その時どきの思いを聞きました。 |  |
「国連の環境会議で、事故当時の状況を話すため、被災者を代表してブラジルに行ってきました」と宍戸さん |
ある日、娘が食事中に突然大量の鼻血を出しました。さらに、1才児の1年間の内臓被ばく予測データが公表されると、100ミリシーベルトの境界線が住んでいる町にかかっていたのです。もう迷いはありませんでした。娘の大好きな野イチゴや桑の実が熟す前にと、6月15日、札幌に避難してきました。
| つなぐことから |
10日後にお茶会を開くと、集まったのは20家族以上。乾杯の後は、みんな一斉にしゃべり出しました。福島を出る時に「私たちを捨てて行くの」「非国民」と言われたことや放射能の恐怖。お互いに地名を言っただけで、原発からの距離や汚染の状況がわかるのは、本当にうれしいことでした。
その後、行政や支援団体の協力を得て、さらに避難者のつながりを広げることもできました。
| 今、福島は |
| 一人でも多く避難を |
避難したくても相談する場がないのなら、こちらから出向こうと、昨年2月、相談会を開きました。意外にも、次々と人が訪れ、新たな避難と保養に結び付けることができました。しかし県は、自主避難する人の家賃補助申請の新規受け付けを、12月末で終了してしまったのです。 今後は自力で引越ししなければならず、別な形の支援や、制度改正の働きかけを検討していかなければなりません。
| 隣人として |
私が住む団地の避難家族は現在170世帯に増え、まわりの町内会とのつながりもできてきています。でも、不安が消えることはありません。先が見えないから、覚悟して帰ることも、北海道に永住することも決められないのです。身内と離れて暮らすつらさもあります。 どうぞ、こういう人たちがいることを忘れないでください。負担にならない範囲でいいので、寄り添って話を聞いてください。「一人じゃない」と思えることが、今一番必要なんです。 (聞き手/佐々木)
| 班っていいね! | 班の良さが見直されている今。長く活動 を続けている班と、今年度新しく誕生し た7班の中から、ひと班を紹介します。 |
はこだてわいんで乾杯した生活クラブパーティー |
「荷受場所は誰でも入れる自転車置き場なので、お互いに 気を使わずに済んでいます」「前は盗難やいたずらの被害も あって、エッコロこは随分とお世話になったけど、今は鍵のかかるボックスに消費材を入れているので安心です」「実は私が加入したきっかけは、10年前にスーパーで自然食品を透明なしジ袋にいっぱい入れていたところ、『値段高いでしょ』と声をかけられ、『もっと安くていいものがあるわよ』と生活クラブに連絡をして、加入までを手伝ってくれた組合員に出会ったことなんですよ。子どもも小さかったので、班に入って、子育ての話や地域の話を聞けてとても参考になりました」「メンバーも40代50代になって、健康についての話題が多くなりましたけどね」。班会の場を提供していた建名さんは「こんなに長く続いているのも、交流が楽しくためになるからでしょうか」と話します。
今日はこの後「戸配組合員を誘って班で生活クラブパーティー」。テーブルにはたくさんの消費材と、手作りの漬物が並んでいます。戸配の組合員2人が参加していました。 (取材/沼田)
江別支部 大麻地区
赤ちゃんが加わると子どもが8人の賑やかな班会になります |
もともと戸配組合員だった岡さん。班の良さを聞いてはいたものの、自分から声掛けすることができないでいましたが、運営委員長の鈴木さんに背中を押され、近所のお宅を訪ねました。「この消費材の良さを誰かに伝えたい、教えてあげたいと、いつも思っていました。どうしても班を作りたかったので、犬の散歩のついでに、勇気を振り絞ってピンポンしてみたんです」と、振り返ります。不思議なことに、皆それぞれ過去に資料請求をしていて、それがきっかけで新班結成と成りました。 「最初は加入に乗り気でなかった夫も、今では消費材がすっかり気に 入っている」とか、「夫がカレーに生卵をかけて食べた時、市販品との違いに驚いた」、「せせらぎをうまく 使えずにいたが、支部の講習会に出て勉強になった」など。皆さん楽しそうに話していました。
雪が降ってからは、荷受け場所にしていた物置が使えなくなって他の場所を試しているそう。まだ初めてほんの数ヵ月。困った時にはお互いさま。みんなで助け合いながら楽しく続けて行きたいものですね。 (取材/坂本)
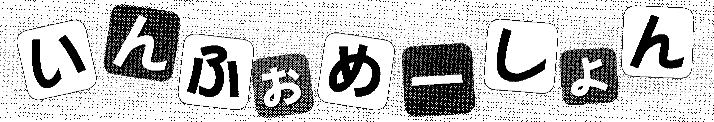 |
チュプ1月号 お年玉付き!クロスワードの答え ヨウリホウ 「容リ法」は容器包装リサイクル法の略 「消費材福袋」の当選者 手稲支部 野口菜穂子さん (お彼岸セット) 東支部 小神麗子さん (ティータイムセット) 厚別支部 大森香織さん (パスタセット) 北広島支部 古舘暁子さん (中華セット) 北支部 木村聖子さん (お好み焼きセット) たくさんのご応募ありがとうございました。応募総数59通の中から 抽選の結果、5名が選ばれました。 問合せ/生活クラブ本部 TEL011-665-1717 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 生活クラブの組合員になって早16年。委員活動に仕事にと、慌ただしい毎日を過ご している。楽しみと言えば、念願叶って、ようやく参加できたゴスペルのレッスン。娘と 二人で通い続け、今年で八年になる。 娘が不登校になり悩んだ時も、母を亡く して悲しみに沈んでいた時にも、いつも慰め られ癒しを与えてくれた。今や、私の生活に は欠かせないもの。昨年末には、メンバー と一緒にNYツアーにも参加した。ふつ-の おばちゃんには考えられない贅沢なこと。我儘をきいてくれた家族にも感謝しなくては。 毎年開催されるライブも数日後に迫った。 今年はなんと二トリホール!指定色の真っ 赤な衣装を手作りし、あとは本番につまずかないことを祈るのみ…かな。 広報委員 坂本 静 |
「つむじ風」に掲載する組合員エッセイを募集します 文字数は300字程度。テーマの指定はありません。 本部 川瀬宛 FAXまたは業務便でお送りください。 |