 |
生活クラブ北海道機関紙 2013 3 NO.362 |
| INDEX | |
| ●2012 後期生産者交流会 「生活クラブが主要品目にこだわるわけ」 | |
| ●2012 福祉基金助成先紹介 (ワーカーズ5団体) 子育て支援びすけっと/子育て支援べりいべりい・企画プラネット/ たすけあいむく/食まどり/たすけあいさくらんぼ |
|
| ●仲間を増やそう!拡大試食会 | |
| ●いどばた テーマ 「子どもの携帯電話」 | |
| ●いんふぉめーしょん |
 3/2生活クラブ本部会議室 |
 |
| 2012年度 後期生産者交流会 1/31 かでる2・7 生活クラブが |
   |
後期生産者交流会が開催され、 15団体37人の生産者と85人の組合員が参加しました。午前は、生活 クラブ連合会会長加藤好一さんの講演、午後からは分科会が行なわれました。(主催本部消費委員会)
生活クラブ連合会会長 加藤好一さん
生活クラブの現状について 話す、加藤好一さん |
今日のテーマの主要品目とは、牛乳・米・鶏卵・豚肉・牛肉・鶏肉・青果物で、最近ではこれに魚介類も加えています。この主要品目が、なぜ生活クラブにとって重要なのか。 それは結集力に関係しています。生活クラブの結集力は年々低下しており、ウルトラマンにたとえて言うなら、今は活動のタイムリミットが迫ってきて、胸のボタンが黄色で激しく点滅しているような危機的状況ではないかと思うのです。
まとまる力
生活クラブは、東京都世田谷区の一角で1965年に誕生し、その後、70・80年代と単協の設立が続き、成長期を迎えます。 しかし、90年代に入って、新たに単協が生まれたり、福祉事業が急成長をとげるにもかかわらず、グループ事業としては停滞期を迎えます。私はその要因は、各地の単協で自立性が高まったのと同時に、まとまりがなくなったからではないかと考えています。
その象徴的な例が、93年に記録的な冷夏で米不足となって起きた平成米騒動です。全国の店頭から米が消えた時、「各地の購買力を集めて、産地と提携して頑張ろう」とするのではなく、各単協ごとに米を調達したのです。けれども、購買力を分散していたら、いずれ自分たちの目指す運動が出来なくなってしまいます。そこでグループ全体で、「もう一度まとまろう」と確認しました。それが主要品目にこだわるということだったわけです。
利用高1人当たり 2万円を切ると・・・
07年度に行なわれた主要品目の利用調査で、当時約115万人の組合員数を抱える首都圏の生協と、32万人の生活クラブとの比較では、米・牛肉・牛乳の年間利用量は生活クラブが上回り、豚肉も桔抗しています。
また、他生協の組合員に向けた購入先調査では、米を除く主要品目の全てが、生協よりもスーパーで購入する人の割合が高いという結果でした。一方、生活クラブ組合員は、米や肉、牛乳、鶏卵などはスーパーではなく、共同購入を利用する割合のほうが高い。
では、もっと利用を増やすためには何を要とするのか。「コープとうきょう」が、組合員の消費行動を調査したところ、週当たり5千円以上の購入者は、野菜を買っていて、野菜が牽引役になっていることがわかりました。組織が高齢化している生活クラブにとっても、野菜は伸ばせる有望分野です。
もう一つわかった点は、やはり主要品目にこだわって、初めて一定以上の利用に達するということです。私は、生活クラブ全体で1人当たりの月利用高が、11年度に2万1千円まで下がってきたことに、非常に危機感を持っています。2万円を切ることは、こだわりが低くなるということ。主要品目にこだわる生協ではなくなることを意味するのです。絶対にそんなわけにはいきません。
課題は仲間づくり
しかし一方では、デフレ経済が続いて世帯年収が減ってきており、中国産など安価なものに目が向いてしまいがちです。
全国の生協が加入する日本生協連は、低価格を目指すために、原料の海外調達や食品添加物の基準引き下げなどを対応方針として掲げています。もはや生協であっても、このようなことが当たり前になってしまう風潮で、生活クラブは頑張っていかなければなりません。 その中で、私たちが強化すべき課題は、共同購入を通した人づくり、仲間づくりです。ネット時代はありますが、やはり運動である以上、人が人に働きかけることは欠かせません。相当の努力が必要ですが、今後も北海道のみなさんと連携しながら進めて、なんとか乗り切っていきたいと思っています。(谷山)
| 福祉基金助成先紹介 | 福祉基金賛同者状況 (2月28日現在) 3,017名(60名増) |
地域で心豊かに暮らしていくための、「生活クラブ福祉基金」は、生活クラブが進める福祉事業・活動の財源となるとともに、地域で福祉活動を進めている団体に助成を行っています。昨年は1年間で賛同者が562名増え、2012年度は13団体に125万円の助成を行いました。 |
| 子育て支援ワーカーズ びすけっと |
微力ながら助っ人になりたいという 思いで名付けた「びすけっと」 |
子どもは親だけではなく、地域や社会と触れ合いながら育ってほしいとの願いを込めて、12年3月に 始動した「びすけっと」。主な活動は、保育の他に小樽市民センターで月 に一度開催する親子ひろばです。 取材に訪れた日は、9組の親子がそれぞれが楽しそうに、絵本やおもちゃで 遊んでいました。中でも福祉基金の助成金で購入した木のおもちゃは大人気。トマトや人参など木のままごとをお目当てに来る親子もいます。 「ひろばに来るお母さん方は口コミが殆どで、リピーターも多いですね。ここに来るとお友だちができるので、みんな楽しみにしてくれています。お母さんも安心してほっとできるひと時が必要だと思 います」と副代表の後藤律子さん。 高いスキルを身につけもっと幅広 い支援をしたい。そして、一人で 悩んでいるママたちにも呼びかけ て、親と同じ目線で一緒に子育て 支援をしていきたいと語ってくれ ました。 (川瀬) |
| NPO法人 たすけあいワーカーズ むく |
| むくは、札幌市白石区で訪問介 護やたすけあい事業を行っていま す。「日々お年寄りと接している中 で見えるのは、自宅に閉じこもリがちな一人世帯が多い事です。中 にはテレどと会話して一日が終わ る、という方もいます」と代表の 大熊薫さん。 そこで少しでも外に出て、地域 とのつながリが持てる場があれば と、昨年の6月、ボランティアを 募り「お茶の間サロン」を始めま した。助成金は力-テンや絨毯、 照明などに使いました。 最初は何かお世話をしなくては と気負い気味でしたが「長続き させるため、もてなすことはやめよう」と方針を決め、現在は火曜と木曜に開き、季節ごとの行 事を楽しんでいます。利用者から は「ここに来ると、皆でご飯が食 べられて、グチも言えてすっきり」 との声が聞かれました。 (加藤) |
 木曜日は100円で具だくさんの みそ汁とご飯が食べられます |
| 子育て支援ワーカーズ べりぃべりぃ 企画ワーカーズ プラネット |
バランスボールを使ってストレッチ |
豊平区で活動しているワーカー ズ2団体は世代を超えた交流の場 を作りたいと考えていました。そ こで共同で企画し、福祉基金の助 成を受けて開催したのが「わらべうたベビーマッサージ」と「みん なで健康ストレッチ講習会」。肩 こりをほぐし、腰を痛めないよう にするための体操は、子育て中の お母さんから高齢者まで一緒に楽 しめる内容でした。また、子ども を自由に遊ばせながら参加できた ことが、親にとっても、小さな子 と触れ合うことのなかった世代に とっても喜ばれました。 また開催して欲しいという声が 多く、ベリぃべりぃの西田眞知子 さんとプラネットの谷口眞子さん は「これからも、地域に密着した 活動を続けていきたい」と来年度 に向けた計画を立てていました。 (沼田・三ツ江) |
| 食のワーカーズ まどり |
| 午前10時半、昼食のおかず 4品が出来上がリ、次々に弁 当箱に詰められていきます。 「から揚げやハンバーグのとき は注文が多いんです」とまど
りの代表富樫正子さん。 04年から北星学園のスミスの中高生約60名に食事を 作ってきましたが、昨年4月 から通学生のための支援弁当 を始めました。毎日作る弁当
は大変で、お母さんの体調が すぐれないときなど、コンビ ニ弁当に頼らないよう、寮生 と同じ弁当を提供したいと、 以前から思っていました。 それが実現したのは一昨年。 福島から避難してきた子ども の弁当を作ってほしいと、学園 側から依頼があったからです。 食材は可能な限り生活クラ ブの消費材を利用し、敬遠さ れがちなお浸しや魚も食べて 食の大切さを支援弁当で 「私たちの活動が広がリ、PT Aの集まりや先生方の研修に お弁当を作って欲しいという依 頼が増えています。卒業生か ら、ここの食事が良かった、と 手紙をもらったときは本当に嬉 しかったです。」現在は学園関 連だけの活動ですが、将来は 地域の人にも食事を提供して いきたいと話しています。 |
ピンクの二段弁当箱を助成金で購入 |
| NPO法人たすけあいワーカーズ さくらんぼ |
「大型絵本は楽しい」 |
さくらんぼは、今年で設立 9年目。重度の障がいを持つ 子どもの移動支援、居宅介護 や訪問介護など、利用者15名 について、9名で対応してい
ます。 代表の齊藤佳代子さんにお 話を聞いている時、放課後の 移動支援を行っているスタッ フから利用者を送り届けたが、 鍵がかかっていて、家に入れ ないという連絡が入りました。すぐに齊藤さんが、その子の お母さんと連絡をとり、おば あちゃんの家で帰りを待つこ とになりました。こういった 急な事態にも、うまく連携を 取り合って対応しています。 助成金の使い道は、スタッフが勉強するために必要な専門書と、大型絵本の購入でした。体力のない子どもたちの移動には、途中でトイレや水分補給の必要もあります。そのため、事務所の一階の部屋 には、立ち寄った際に遊べる よう、絵本やおもちゃなども 用意してありますが、大きな 絵本があれば、視覚に障がい がある子でも見られます。 将来は、一軒家を借りて生活全般の介護ができるような 形にして行きたい。そのため の体制を整えたいと、今、新し いメンバーを募集しています。 (坂本) |
| 白石 |
仲間を増やそう! 拡大試食会 提携生産者と共に消費材を使った料理で、未加入の友人・知人に生活クラブの良さを知ってもらおうと、各支部で拡大試食会を開催しました。 |
江別 |
| 中央 ㈱NSニッセイ・石川養鶏・木田製粉㈱ 生産者さん教えて! 生活クラブと市販品の違いは? 2/1札幌エルプラザ |
事前の、過去の拡大イベント来場者への呼びかけやお便り、新規加入者歓迎会や地区会、機関紙での呼びかけにより、組合員が9名の知人を誘って参加しました。 当日は三生産者それぞれに、こだわりや熱い思いを語っていただきました。 NSニッセイでは徹底した冷凍管理による鮮度の違いや、添加物を使わず丁寧に作っていること。石川養鶏からは、平飼い・開放鶏舎・密飼いの利点や欠点・遺伝子組み換えの怖さ・自前で作る飼料の安心さなど。木田製粉は、粉砕からふるいにかける作業を繰り返し、手間をかけて作っていることやポストハーベストの問題など。 生産者に3つのテーブルに分かれてもらい、参加者が各テーブルを30分ずつ回り、試食しながらお話を伺いました。生産者の生の声にはみんな興味津々で、質問も次々飛び交い、あっという間でした。 その後は、消費材で作ったチヂミを食べながら交流し、いい雰囲気の中、組合員が生活クラブの良さを伝えてくれたので、その場で2名が加入となりました! アンケートの感想も好評だったので、今後も開催できるといいと思います。 運営委員 宮田あい子 |
| 当日は、あいにくの雪でしたが、事前に新聞に折り込みチラシを入れ、また組合員を通して直接の声がけを行った結果、組合員以外の7名の他、生産者も含めて総勢29名が参加。 まずパルナパフーズからは、添加物についてはもちろんのこと、ウインナーなどに使われる豚肉や与える飼料など、市販品との違いについて説明がありました。 2番手は、東しゃこたん漁業協同組合。魚は水揚げ後、すぐ冷凍するので大変鮮度が良いという内容でした。目の前でほっけを開く実演もあり、手際のよさに、皆で見とれる場面もありました。 最後を飾ったのは由仁いちろう会。しいたけというと、地味な印象があったのですが、原木栽培と菌床栽培との違いや、原木の種類や産地にもこだわっていると聞き、「もっとしいたけを食べたい!」という気持ちにさせられ、皆さん熱心に聞き入っていました。 その後は、立食形式での試食会。最初は遠慮がちだった参加者も良い香りの中、質問も飛び交い、美味しさを実感。皆がそれぞれ楽しむことが出来たようでした。加入にもつながり、収穫の多い1日になりました。 運営委員 佐藤真希 |
北広島 札幌バルナバフーズ㈱・ 東しゃこたん漁業協同組合・由仁いちろう会 生産者に 聞いて発見! 食べて安心! 生活クラブ  |
新登場! |
組合員のおしゃべりコーナー ここ10年程で、世の中にすっかり普及した携帯電話。便利な一方、普及の速度 が早過ぎてマナーやルールは後手の状態。また、子どもに持たせることで、いじめ やケータイ依存、高額請求、さらに犯罪に巻き込まれるなど、さまざまな危険に子 どもをさらしています。そして、その実態を親も把握しきれていないのが現状です。 新企画「いどばた」では、子どもの携帯電話にまつわる親の思いや、持たせる際の ルールなどを寄せてもらいました。 |
| テーマ 子どもの携帯電話 |
| インターネットを禁止していたのに、中2の子が、ゲーム機でブログを作っていた。書き込みが原因で友達とトラブルを起こし、一人ぽっちに。可愛そうに思い、条件付で携帯電話をもつことを許してしまった。 友達の悪口や噂話をメールしない。ツイッターやブログへの書き込みをしない。そして、夜 10時になったら、親に預けるとしたものの、日中は常に携帯をいじっている。誰とメールしているのか、どんなサイトを見ているのか…。もう、トラブルを起こさないことを願うばかり。 (ラチとらいおん) |
 |
| 電磁波、出会い系…できれば持たせたくなかったのに。夫が中学生だった子に誕生日の プレゼントとして買い与えてしまった。奔放な子は四六時中携帯を放さず、壮絶な親子バトル
があった。母のアドバイスはう るさい説教でしかなく、反発と 断絶しか生まなかった。急がばまわれ。「あなたが大事」と言葉 と態度で発信し続け、自分の意見
は我慢して、子どもの気持ちを根 気よく聞いた。関係を修復してか ら伝えた「あなたが心配だから」 は、スーッと届いた。 いや-、それまでに何年かかっ た事か。紆余曲折し、子どもも今 や成人し上手に携帯を使いこな しています。 (きぬ) |
私は、電磁波過敏症というア レルギーです。携帯電話や 家電製品、電車などから出る電磁波の影響で、頭痛や疲労感な どの症状が出ます。電磁波は放 射能と同様、発ガン性があり、
遺伝子を切断します。 アメリカで実施された追跡調査では、妊娠中、出産後とも携帯を使用した母親から産まれた子供は、行動障害を持つ確率が 50%高く、子供が早い段階から 使用し始めた場合の行動リスク はさらに高まるというデータが出 ました。近年、私のまわりでも増 えている過敏症に悩む人達や発達障害児の多さとも無関係では ないと思います。 (戸谷真知子) |
| 15歳の娘は、中学入学と同時 に携帯を持ちました。ローカルな私はまだ持たせたくな かったのですが、仲の良い友達 全員が持っており「話について いけない」 と娘に泣きつかれ、
しぶしぶ持たせました。その際 に決めたルールは、食事中と勉 強中はメールを見ない。料金が 2千円を超えたら自分で払う。 友達の悪口を書かない。10時以
降は使わない。 このルールのおかげか、必要な 連絡をする時以外携帯を使わな いローカルな娘に成長しました。 (本間真由美) |
塾の送り迎えのため、娘には 小学5年生から携帯を持たせています。不安に感じる使い方をせず安心していたのですが、 中学入学後、ある友達とメール アドレスを交換したことで一変、
夜遅くまでメールするように なったのです。その子は娘以外 にも頻繁にメールを送るようで、 問題になっているそうです。 元々メールをするのが苦手な 娘は「親に怒られて携帯を取り上げられた」と伝え、今は断っ ているようです。 (たぬきの母) |
| 携帯電話、今は高3の娘と、 中3の娘が持っています。 長いバトルと話し合いの末に、 こちらが折れて持たせたのです が、近頃はGPS機能のためか
身近な所で小学生も普通に持っ ていることにびっくりします。私 はまだ子どもが持つことに納得 していないのかもしれません。 携帯電話会社も、もっとシンプルな機能のものを取り扱うようにしてほしいです。(そらマメ) |
※次回のテーマは「私の健康法」です。 ご意見をお寄せください。 |
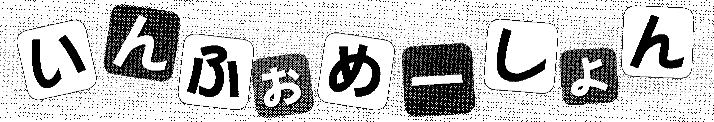 |
問合せ/生活クラブ本部 TEL011-665-1717 |
福祉基金助成団体が決まりました!
|
 列車に揺られて過ごす、およそ1時間は貴重 だ。資料を読んだり、睡眠不足を補ったり。な んと言っても二人掛けの座席が落ち着くが、今 はロングシートが主流になってしまった。これだ と向かい側に座る人がまる見えだ。 午前中の車内は新聞を読む人、眠っている人、 時にはお弁当を食べる人もいる。近頃多いのは 手元のケータイを見つめる人。5、6人の知らな い者同士が、横並びで一様に同じ動作をする光景 はなんとも異様だ。 ところが、赤ちやんが乗っている日の空気は まるで違う。赤ちやんの笑顔は、まずお年寄り やおばさんに伝わる。渋い顔をしていたおじさんや、すましていたお姉さんの顔もほころぶ。 いつの間にか車内が明るくなり、心まで軽く なってくる。 赤ちやんって、すごい…。おっと、発寒駅に到着。 広報委員 佐々木 さゆリ |
「つむじ風」に掲載する組合員エッセイを募集します 文字数は300字程度。テーマの指定はありません。 本部 川瀬宛 FAXまたは業務便でお送りください。 |